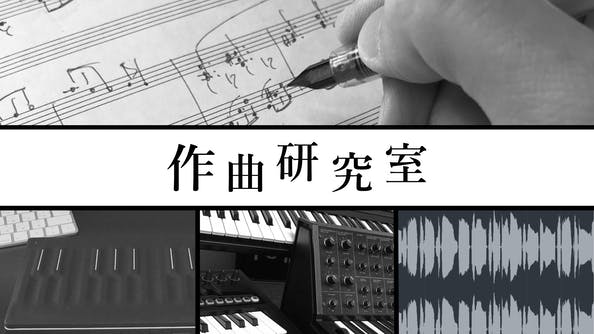こんにちは、よしたく先生です。
卒業式や入学式の時に聞く『君が代』ですが、歌詞については気にすることがあっても、音楽的にどう作られているかを考えることは多くないと思います。
私自信「『さざれいしの』ってどういうことだろう」「『いわお』って人の名前かな」くらいにしか考えていませんでした。
そこで今回は、君が代の音楽的な分析をしてみたいと思います。
『君が代』について
改めて曲を聴いてみると何ともおごそかな雰囲気があります。編曲は近衞秀麿で、ヤマハから楽譜が出版されています。
この『君が代』の旋律は1880年に作曲されましたが、正式に国歌として定められたのはおよそ100年後の1999年のようです。
その他の細かな説明についてはWikipediaを参照してください。
曲の分析
調性(ハ長調とか)のある曲は旋律の最後の音をみると何調か判断することができます。
この曲はレの音で始まってレの音で終わっているので、ニ長調かニ短調の曲のはずです。
ただ、調号をみると何も書かれていません。ニ長調なら♯が2つ、ニ短調なら♭が1つついているはずですし、臨時記号も何もついていません。

実はこの曲は、長調でも短調でもありません。雅楽のレの音の呼び方(壱越)から取った壱越調の曲です。
旋律が雅楽の音の並びで作られているので、クラシック音楽にあるようなドミソとか、ファラドといった和音をつけることができません。
この曲の最初と最後を改めて聴いてみると、和音らしい和音はついておらず、旋律だけが演奏されています。
これは和音をつけてしまうと違和感が出てしまうからだと考えられます。
和音を付けてみる
それなら、実際に和音をつけてみたらどうなるのか実験してみましょう。最後がレで終わるのでニ長調、ニ短調、ト長調、ト短調の4種類の伴奏をつけています。
下の動画は実際に伴奏をつけている部分のみ再生されます。
ニ短調やト長調の伴奏がマシに聞こえますが、どれを聴いても終わった感じがしないのではないかと思います。
つまり和音をつけること自体はできるが、違和感が出てしまうので決定的な部分には和音をつけていないということになります。
おまけ
リオオリンピックの閉会式では『君が代』がかなり不思議な響きにアレンジされていました。
作曲家の三宅純さんのアレンジで、こちらからインタビュー記事を読むことができます。
無伴奏の4声の合唱ですが、東洋の響きもあり、ジャズっぽさもあり、とにかく不思議な雰囲気です。
参考文献
小泉文夫著『日本の音』平凡社,p.289.